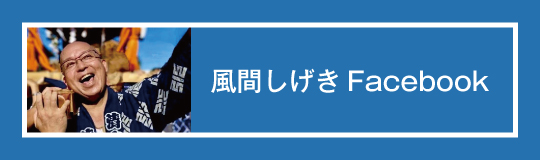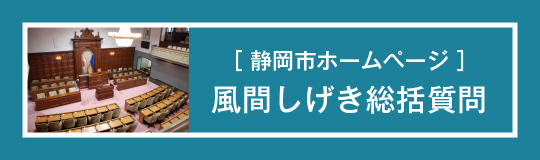プリズム
このまちの未来について、風間しげきが思うことを綴っていきます。皆様のお声もぜひ、お聞かせください。

BayPRESS 852号 /2018年09月08日発行
「静岡市はいいねぇ」 郷土思う気持ち大切に
「さくらももこさんが亡くなりました。」会議が終わり、携帯に残されていたメッセージは知人の新聞記者からだった。 「ご本人と関係のある方のコメントを至急取りたいのですが、どなたか…」聞き終わらないうちに、言いようもない寂しさを感じた。
清水区民の多くが同じ気持ちだったと思う。まるちゃんの暮らしを、とても身近に感じながら、同郷のさくらさんの活躍を誇りに思っていた。
岡小学校の地域公開授業で小学校3年生の子供たちに「まるちゃんの町は大洪水の巻」を引用し、七夕集中豪雨の話をした。入江小学校への通学路にあった歩道橋の上から見た風景も、写真に収め子供たちに見せた。さくらさんが好きだったといわれる景色だ。
視察で県外に行くときには、議員の多くが「静岡市はいいねぇ。さくらももこ」と書かれたイラスト入りの名刺を持参した。かわいいイラストは久能山東照宮、模型の世界首都、さくらえび天日干し…、視察先で必ず話題になった。
さくらさんが愛した清水、郷土を思う気持ちを大切にしたいと思う。心からご冥福をお祈り致します。
BayPRESS 851号 /2018年08月25日発行
借金残高は増加傾向に 建設事業と住宅ローン
市が今後、立て続けに建設を予定している、市役所新清水庁舎や水族館を核とした海洋拠点文化施設(清水区)、歴史施設や文化会館の建て替え(葵区)などは、いずれも数十億から百数十億円規模の経費が見込まれている。
大型建設事業などを行う際に、市は資金調達のために借り入れを行う。市の借金が増えると、将来の負担が大きくなり、時代の変化に伴う出費を工面するのが難しくなっていく。
住宅ローンと同じ。家を建てる時、一家の将来にわたる収入や子供の成長に伴う教育費、急な病気や家屋の修理なども十分に考慮するはずだ。
人口も税収も右肩上がり、高度成長期ならともかく、これからこの街を担う子どもたちの肩には、人口減少に伴う税収減、高齢者福祉に対する費用負担増などが重くのしかかる。
静岡市の市債(借金)の残高は平成28年度決算で4482億円。増加傾向にある。
私たちが将来にわたって本当に必要とする規模、内容の施設なのか。負担はどうか。
全国の市町では、大規模建設事業を見直す取り組みが進んでいる。
BayPRESS 850号 /2018年07月28日発行
集中豪雨で大谷放水路 先憂後楽は必要な資質
西日本豪雨による死者は20日現在で219名。亡くなられた方々のご冥福と、今なお避難所に身を寄せている方々が、一日も早く日常の生活に戻れるよう心から祈りたい。
1974年静岡市。7月7日から8日にかけて降った雨は508ミリを記録した。
高校一年の夏だった。雨続きだった野球部の合宿が終わり、友人たちと七夕見学に出かけてた。突然降りだした雨は傘が差せないほど激しくなった。巴川の堤防をこえた濁流が町に流れ込む光景を目の当たりにした。
七夕集中豪雨。この災害で27名の尊い命が失われた。
1978年、巴川は全国初の「総合治水対策特定河川」に指定され県と市は大規模な河川改修工事に着手した。
大谷放水路。総事業費553億円。七夕豪雨から25年をかけ1999年に完成。葵区古庄付近で巴川から分流し、出水時には毎秒150トンの水(約2秒で25メートルプールを満たす水量)を駿河湾に逃がす。過信は禁物だが成果は大きい。
「先憂後楽」…先見力を持って誰よりも先に危機を察し、後の平安を見て楽しむ。リーダーに必要不可欠な資質だ。
BayPRESS 849号 /2018年07月14日発行
若者は観光親善大使 郷土へ愛着と誇りを
「今度、静岡に寄るんだけど、どこか良いとこ教えて」
「う~ん。思いつかないな~」
先日、久能山東照宮権宮司姫岡恭彦さんとの雑談の中で、県外から参拝に来た学生たちとの会話が話題となった。
学生たちは「三保の松原、日本平の風景、そして、荘厳な東照宮の社殿、どれをとっても素晴らしかった」と興奮気味に話し、「なぜ、静岡出身の友人が思いつかなかったのか不思議」とも。
話を聞いて「どきっ」とした。学生時代、友に故郷の良いところをどれだけ語ってきただろう。
市教育委員会学校教育課では小学5年生から中学3年生を対象とした「しずおか学副読本」の作成に取り組んでいる。
「副読本は徳川家康公を含む郷土史や、山間部の魅力を伝えるオクシズ、前浜のことを知るしずまえ、など6分野に分けて編集を進めています」と話すのは石井康義指導主事。来年度から、学校のパソコン画面で学ぶことができる。
進学や就職で市外に出ていく若者たちは、静岡市の観光親善大使でもある。
「郷土への愛着と誇り」を育てる副読本の完成がとても待ち遠しい。
BayPRESS 848号 /2018年06月23日発行
歴史の伝承を担う 次郎長翁を知る会
次郎長翁を知る会(山田倢司現会長)の総会に出席した。
明治元年9月18日、清水港内で起きた咸臨丸事件の犠牲者を葬るため、次郎長が壮士墓を建立してから今年で150年になる。
今年度は9月17日に記念事業が行われるほか、次郎長史跡の探訪事業や次郎長巷談の開催などが予定されている。
総会資料によると、同会の源流は古く昭和3年、梅蔭寺内に次郎長銅像を建立した「精神満腹会」。銅像は太平洋戦争で供出され、昭和27年に「次郎長顕彰会」によって再建された。
その後、次郎長没後百年にあたる平成4年に顕彰会再結成の話が服部令一氏(次郎長生家)、府川松太郎氏(追分羊かん)から上がり、発起人として七代目鈴木与平氏(鈴与)、後藤磯吉氏(はごろもフーズ)、佐々木哲雄氏(清水銀行)、竹内宏氏(長銀総合研究所 初代会長)、林仁山(梅蔭寺)の5氏が名を連ね、次郎長翁を知る会が設立された。
現会員数は108名。「次郎長の事を知らない若い方や、歴史が好きな方は是非」と山田会長。年会費は二千円。
事務局(公財)するが企画観光局清水事務所
BayPRESS 847号 /2018年06月09日発行
幸福度ランキング13位 体系的な対策必要
「全47都道府県幸福度ランキング2018年版」が東洋経済新報社より刊行された。 政令指定都市別では全20政令市中、浜松が総合1位、静岡市は13位だった。
浜松市は財政健全度など自治体の基本的な力を示す基本指標で3位、健康診査受診率など健康分野で2位、家族や地域社会のつながりを表す生活分野で3位と高順位だった。
一方、静岡市は基本指標が14位、雇用環境など仕事分野が13位、国際会議外国人参加者数など文化分野が14位。生活分野では2位だったが、総合順位で及ばなかった。
同社オンライン編集部は「基本指標は、人口動態や所得、財政健全度など、都市の持続可能性や住民生活の根幹を支える重要な都市の土台。各都市が抱える課題等を的確に捉え、状況に即した総合的かつ体系的な対策を講じることが求められる」としている。
静岡市では大型の建設投資が立て続けに予定されている。市民の幸福度を高めるため、総合的かつ体系的な計画となっているのか。厳しい財政状況下、後世に中途半端な施設と借金だけが残ったと言われぬよう、議会審査のハードルは高くあるべきだと思う。
BayPRESS 846号 /2018年05月26日発行
次郎長の力 今なお衰えず 生家 文化財指定受け市へ
清水港の礎を築いた次郎長の生家が、国の有形文化財指定を受け静岡市に寄贈された。
老朽化が進み早急な改修が必要となっていた生家。「何とか後世に伝えたい」との思いを子孫で所有者の服部千恵子さんから聞き、6年前有志たちが「次郎長生家を活かすまちづくりの会」を立ち上げた。
「まずは雨漏りだけでも直したかった」と話すのは、同会の牧田充哉理事長。最初は顔見知りの個人や企業商店回りから始めた資金集めも、しばらくすると、「後藤磯吉・悦子福祉及び教育奨励金」の活用や、耐震住宅100%実行員会(東京都港区)、清水北ロータリークラブ、清水銀行、鈴与株式会社、フジ物産株式会社など大きな支援先に繋がっていった。
「人が人を呼んだ。奇跡的ともいえる展開だった」と牧田会長は振り返る。「腹を据えれば何でもできる。そんなことを、教えてくれた…」。
清水の次郎長は人を魅了する並外れた力があったのだろう。その力、今なお衰えず。2020年は次郎長生誕200年の年に当たる。清水の宝が一つ新しく生まれ変わった。生家をいかしたまちづくり、今後の活動に期待したい。