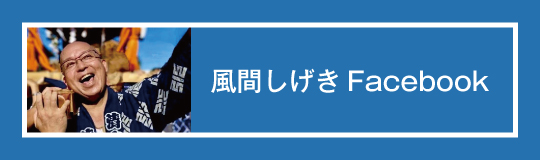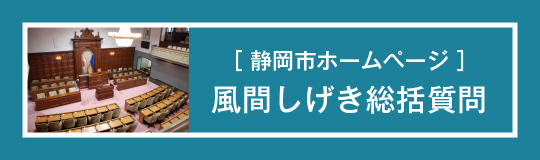プリズム
このまちの未来について、風間しげきが思うことを綴っていきます。皆様のお声もぜひ、お聞かせください。

BayPRESS 898 899号 /2020年10月24日発行
構造的耐震性能は新耐震 現清水庁舎建設時の思い⑥完
「清水市からは、東海大地震に耐える市庁舎を要求された。当時最先端の設計を納品した」
37年前、現清水庁舎を設計した㈱佐藤武夫設計事務所(現㈱佐藤総合計画)の構造部長と清瀬市で面談した。
「まだ新耐震施行前の計画通知であったので、法律の形式上は旧耐震となるかもしれないが、構造的耐震性能は新耐震に適合させてある」。
平成24年に市が実施した耐震診断で構造耐震指標が、倒壊または崩壊する危険性があるとされる数値に近かった点について「耐震指標は、旧耐震建物を解析した場合の統計的な数値。清水庁舎の耐震性能を明らかにしたものとはいえない」といなした。
より詳細な耐震診断が必要かとの問いには「庁舎は市民全員の財産で、私有財産ではない。当局だけの判断ではなく、市民全員が納得できる耐震診断が必要だ」と話し、「解析には費用がかかるが、ほとんどの市民が納得できる解析手法であれば、有意義なものとなるだろう」と自信をのぞかせた。
移転計画は一時停止中だ。市が現庁舎を「耐震性能に問題がある」と断定した以上、詳細な耐震診断が必要だ。(完)
BayPRESS 897号 /2020年09月26日発行
診断法の限界と不可解な点 現清水庁舎建設時の思い⑤
耐震診断には、一次、二次、三次診断があり、一般的に、 一次は簡易な診断、二次は校舎など鉄筋コンクリート造向きの診断。三次は現庁舎のような鉄骨鉄筋コンクリート造向きの診断といわれる。
現清水庁舎には二次診断が用いられた。市は「県基準では原則二次診断で良いとしている」としているが、現清水庁舎のような特殊な構造の場合には、適切な評価をするよう求めている。
「二次診断で清水庁舎の耐震性能を表すには限界がある」と前出の建築士。
「例えば、現清水庁舎は地層と133本の基礎杭、地下室が制震装置として働く設計となっているが、二次診断ではこの部分が考慮されない」
耐震診断の報告書にも、二次診断の結果と、詳細な診断の結果は異なる可能性があると記されている。
建築士はさらに、二次診断そのものにも不可解な部分があると話す。「一階部分の地震に耐える力を示す数値が設計図書の数値に比べあまりにも小さすぎる。この数値では中規模の地震でも壊れてしまうことになる」
耐震診断の目的は何だったのか。現清水庁舎の設計責任者からも、より詳細な診断を望む声が聞かれた。続
BayPRESS 896号 /2020年09月12日発行
レントゲン診断で死亡宣告? 現清水庁舎建設時の思い④
田辺信宏市長は住民投票条例設置請求に付した反対意見の中で、改めて現庁舎の耐震性能不足を移転新築の大きな理由にあげた。構造設計上に問題はない。だとすれば躯体の経年劣化が影響を与えているのか。
平成29年の市議会本会議で財政局長は「平成24年にコンクリートの圧縮試験と劣化度の進行状況確認のための中性化試験、および内外壁のひび割れ等を確認するための外観目視を行った。結果は良好で問題はない」と明言した。
しかも、その時の調査報告書によると、コンクリート強度は設計当初の強度を上回る数値をはじき出していた。良質のコンクリートは築年数が増すほど強固になるという。
さて、当初から大地震にも耐える事を条件に設計され、躯体の劣化も進んでいない。それでは、なぜ移転新築しなければならないほど、耐震性能が劣るのだろうか。
この疑問について、前出の設計士は「市当局が委託先に指示した診断方法が、そもそも現清水庁舎の構造に適しているとは言えない」と指摘。「レントゲン診断で写った影を癌と診断、精密検査もしないでいきなり死亡宣告を受けたようなものだ」と、ため息をついた。続
BayPRESS 893 894号 /2020年07月25日発行
住民投票条例否決 移転予算は白紙へ
「市民に賛否を聞く必要はない!」。住民投票条例案は賛成8名(創生静岡4名、共産党3名、緑の党1名)、反対37名(自民党24名、志政会7名、公明党6名)で否決された。
市長も議会も「市民の意見集約は十分に図られている」と言うが、疑問は残ったままだ。多額の市税を投じる大規模事業に反対の声も多い。前提として納税者の過半数の賛成は得られているのか。
住民投票を求める有効署名数は、衆議院議員選挙での中断やコロナ感染拡大防止による自粛という状況下で5万2,300筆に上った。また、これまでに行われたマスコミの世論調査でも、移転反対が賛成を上回っていた。
市は市民に移転の賛否を一度も聞いていない。最初から最後まで強引に計画を進め、議会もそれを追認してきた。
住民投票は間接民主主義を「補完」する制度だ。市長や議員が公正な選挙で選ばれ、市政運営を委ねられていることは否定しない。
しかし、前回の市長選挙の投票率は48.76%、市議選は41.16%と過半数を割った。結果や選挙戦での公約をみても明確に推進との姿勢で信任を得たとは言い難い。市長も議員も市民の意向を確認することから「逃げ続けている」と言われても仕方がない。
さて、「清水庁舎移転予算白紙へ」静岡新聞が8月22日朝刊で抜いた。9月には計画の方針が明らかになる。面子を大切にする静岡市政が計画の撤回をするとは考えにくい。コロナ収束を待って事業再開、数年延期でお茶を濁す意向かも知れない。
BayPRESS 893 894号 /2020年07月25日発行
耐震性、津波対策に重点 現清水庁舎建設時の思い③
庁舎完成の前年の昭和57年11月、建設省が監修した「建築技術」誌に興味深い論文が掲載された。タイトルは「清水新庁舎の構造設計~入力地震動と動的解析~」。執筆は清水庁舎の設計にあたった佐藤武夫設計事務所の構造部。
昭和53年の大規模地震対策特別措置法により清水市が地震防災対策強化地域に指定されたことに触れ、設計方針を次のように記した。
「新市庁舎が地震災害時に中枢的役割を果たす防災拠点として十分に機能するように、動的な解析結果を踏まえ、要求される耐震性が確保されることを条件とした」。
また、津波対策については「電気室・発電機室を4階に、中央防災センターを2階に設け、津波時にも重要施設部が冠水することがない計画とした」。
さらに、昭和58年10月、現清水庁舎完成時に同設計事務所が提出した概要書「清水市新庁舎~庁舎の計画から完成まで」では、「建物は中小地震時(震度5程度)では全く被害は受けない。大地震時(震度7程度)で、建物の一部に亀裂が生じるが建物の機能には全く支障がないものにした」とし、昭和56年改正の新耐震規準に準拠した庁舎であることを強く印象付けた。続
BayPRESS 891 892号 /2020年06月27日発行
耐震構造の第一人者就く 現清水庁舎建設時の思い②
昭和58年4月1日、清水市役所(現清水庁舎)が正式に業務を開始した。総工費約62億円。静岡新聞朝刊に「温かみを全面に 随所に身障者への配慮」の見出しが躍った。
当時の稲名嘉男清水市長は「24万人の尊い財産」と題し「財政事情の厳しき折、多額の経費をかけ建設したものでありますから、24万市民の尊い財産として末永く大切にしてまいらねばなりません」と新たな決意を寄稿した。
清水市役所の建設は業界も注目した。世界的に有名な丹下健三氏設計の庁舎(昭和29年完成)を、耐震不足を理由に建て替えるという理由だけではない。昭和56年6月1日、大規模地震を想定した建築基準法の大改正、新耐震基準への移行をまたいで設計施工された大型建設事業だった。
佐藤武夫設計事務所が基本設計に着手したのは昭和55年9月。市行政からの厳しい要求に加え「新耐震基準を超えなければならないという緊張感が張り詰めていた」と当時を知る設計士は振り返る。
その想いは人を繋いでいった。県の紹介で設計監修には日本における耐震構造の第一人者が就いた。梅村魁(はじめ)東大名誉教授(当時)。建設省の依頼で新耐震設計法を作った中心的人物だった。続
BayPRESS 890号 /2020年05月30日発行
世界のタンゲを壊し耐震へ 現清水庁舎建設時の思い①
コロナ対策を理由に新清水庁舎の建設計画が一旦停止した。経済への影響は深刻で長期化を覚悟しなくてはならない。現清水庁舎は使い続けることを前提に再検討すべきだ。 築37年の清水庁舎は本当に「耐震性に問題があり、補強するより建て替えたほうが良い」とされる建物なのか。
市当局はが現庁舎の耐震性能について「建物自体は倒壊する危険性は低いが、かなりの被害を受ける」と説明する。
かなりの被害とはどのような状態か。平成29年3月の総務委員会で公共資産経営課長は、「被害の程度をもう少し具体的に言うと、つり天井等が落ちる可能性は否定できないがその程度、大きな被害は起こらないだろう」と答えている。対策は十分可能だ。
現庁舎の前、旧清水庁舎は「世界のタンゲ」と言われた丹下健三氏の設計。「国立代々木競技場」も氏の設計。
その庁舎を壊してまで、現庁舎に建て替える理由は「大地震にも耐える」ことにあった。設計は㈱佐藤武夫設計事務所(現株式会社佐藤総合計画)。天津オリンピックセンタースタジアムやエコパアリーナを手掛ける設計集団。 次回以降、現清水庁舎がどのような思いで設計されたかを振り返る。続