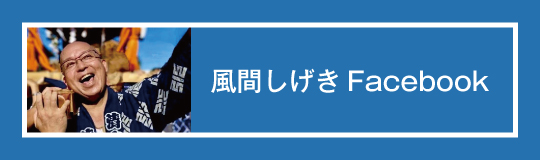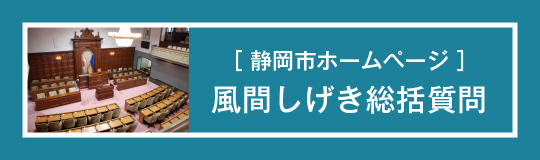プリズム
このまちの未来について、風間しげきが思うことを綴っていきます。皆様のお声もぜひ、お聞かせください。

BayPRESS 817号 /2017年02月14日発行
4日より区民説明会 市長の考え明確に
4日の高部地区を皮切りに、区内8か所で始まるタウンミーティング。庁舎・桜ヶ丘病院の移転等、市長は関連情報と自身の考えをどこまで明確に示せるか。区民が納得できる説明を期待したい。
【移転後の新病院の規模】新病院の病床数、診療体制(現在は199床。産婦人科、小児科は閉科中)。清水病院への影響。
【救護病院の機能維持】懸念される周辺津波被害への見解。救護体制の再整備、津波避難計画の見直し(スタッフ・患者搬送ルートの確保。桜が丘高校に開設する準病院機能を持つ救護所等)。防潮堤の整備・巴川の落橋対策等県との調整。
【新庁舎建設計画】現庁舎の耐震性、移転の緊急性、改修・解体費用。新庁舎の機能と規模、地震・津波対策。建設手法と想定費用、LNG火発の影響(庁舎を高層マンションと一体的に建設、借地料で庁舎建設費を賄う計画がある)。
【都心の賑わい】新庁舎の想定職員数、年間来庁者数(現庁舎の職員数は約千名。年間来庁者数は約40万人)。新病院の想定医師・職員数、年間来院者数。新庁舎、新病院建設完成後に想定される周辺の賑わい。クルーズ拠点と病院の整合性。新サッカースタジアム実現に向けての取り組み。日程は市広報課?221-1487
BayPRESS 816号 /2017年01月21日発行
隠された部分の説明急務 押し出しで清水庁舎移転
桜ヶ丘病院の移転問題は、田辺市長が優位とした「清水庁舎案」をJCHO(病院の運営母体)が支持したことからほぼ方向性は固まったかに見える。あとはJCHOの正式決定を経て、押し出しのカタチで清水庁舎がJR清水駅東口に移転新築される。
「決定するのはJCHOであり私ではない」との立場を崩さぬ田辺市長。結果的には清水庁舎の移転までJCHOに決定付けさせたことになった。
この件は既に本市の危機管理、清水区全体の災害医療の在り方、まちづくりを問う問題として多くの区民の関心事となっている。もはや一部地域住民のみの問題ではない。
救護病院の機能をどのように維持するか具体的な説明はない。清水都心の活性化になぜ病院が役立つのかも理解に苦しむ。仮に清水庁舎が移転するとしても、その跡地は国際海洋拠点エリアに相応しい、賑わいの施設の在り方を議論すべきではないのか。
田辺市長は市民のコンセンサスを得る義務がある。病院移転は防災上一刻の猶予も許されない。にもかかわらず、隠された部分があまりにも多い。早急に市長自らが明快な説明をすべきだ。
BayPRESS 814/815号 /2016年12月17日発行
紙面編集にも新陳代謝 J1復帰で躍進の年に
清水区民にとって、今年一番の明るい話題はエスパルスのJ1復帰。この勢いに乗って、新たな年を躍進の年に。
さて、あっという間の一年。年をとるほど一年が早く感じるのはなぜでしょう。分子生物学者福岡伸一氏は「年齢とともに新陳代謝のスピードが衰え、体内時計の秒針は遅くなる。実際の時計はいつも同じ速さで進むから、気が付いたらもう一年が経っていたということになる」といいます。
新陳代謝とは古いものが新しいものに次々と入れ替わること。人間の体は新陳代謝をしておよそ3か月で生まれ変わるといわれています。しかし、このサイクルは年齢とともに遅くなり、例えば皮膚の場合、20歳代では28日周期なのに対し、50歳代では75日周期になってしまうとこのと。
新しいものを取り入れるためには、一方で古いものや考えを捨てることが大切。
ベイプレスは来年創刊37年。過去にとらわれず、新たな気持ちで紙面を編集していきます。「日々是新(ひびこれあらた)」 スタッフ一同新たな気持ちで新鮮な生活情報をお届けできるよう努力してまいります。
BayPRESS 813号 /2016年12月03日発行
重傷者を津波浸水想定地域へ 病院側の良識ある判断に期待
4日は地域防災の日。岡地区連合自主防災会(堀谷一世会長)の訓練では二中グラウンドと岡小体育館を訓練会場に、小中高生を含む2,120名の参加を予定。初期消火、炊き出し、救護、水槽操作まで、幅広い訓練を行う。
今年は日本列島いたるところで大きな揺れに見舞われた。11月22日には福島県沖を震源とする最大震度5弱の地震が発生。津波警報が発令され約51万人に避難指示・勧告が出された。川を逆流する津波の映像、繰り返し避難を呼びかけるTVアナウンサー。6年前の恐怖が頭をよぎった。
まずは、家屋や家具の倒壊から自らの身を守ること。水や食料、着替えの準備も必要だ。次に、避難所での助け合い。そして、最後に公的機関の援助。自助、共助、公助それぞれの機能が連携し、初めて被害は最小限に抑えられる。
しかし、重傷・重病者は一刻も早く公的病院の助けが必要となる。
田辺市長は救護病院である桜ヶ丘病院の移転候補地の一つに、津波浸水想定地域の清水庁舎の場所を挙げた。市長の言う「災害に強いまちづくり」とは何か。病院側の良識ある判断を期待したい。
BayPRESS 811号 /2016年11月05日発行
清水に職人気質がずらり 念入りに納得できるまで
先週末、清水駅東口イベント広場で行われた清水職人まつりの反省会に参加しました。主催は清水建設産業組合(神谷明宏組合長)。同組合は清水で活躍する家造りの職人集団。基礎工事から、屋根、骨組み、内装、家具、外壁、風呂、畳、石材と11の職種で構成され、小人数では難しい安全への取り組みや、技術の向上、後継者の育成など集団の力で支えあう組織です。
自分の技能を信じて誇りとし、納得できるまで念入りに仕事をする実直な性質のことを職人気質(かたぎ)といいます。最近、聞かなくなった言葉ですが、この組合にはそんな人たちが、ずらり…、しかも…、話が面白い…。区内には住宅関連の仕事をする会社が数多くあり、それぞれの技能に誇りを持つ、そんな職人たちが深く関わっています。
新築やリフォーム、あるいは修繕にしてもまとまったお金が必要になります。そんな時はぜひ、清水に根を下ろし誠実に仕事をする職人たちの存在を忘れずにいてほしいと思います。
ベイプレスでは地元の工務店や職人さんを応援するコーナーを企画、掲載していきます。お楽しみに。
BayPRESS 810号 /2016年10月22日発行
好奇心や想像力を伸ばす教育 先生方に責任と自信、余裕を
岡小学校のゲストティーチャーとして3年生に「小さな発見」について話した。「私の友人T君は、大学生に動物や魚が住む環境について教える偉い先生だ。小学生のころ、一緒に大沢川で小魚などを取って遊んだ。その時好きだった遊びが今のT君の仕事に結びついている」。そんな昔話しを中心に、身の回りの小さなことにも興味を持つ楽しさを話したが、伝わったかどうか。
子どもたちは話の内容より、資料を映すために使ったパソコンや機材に興味があった。スクリーンで影絵遊びをする子、レーザーポインターで遊ぶ子、パソコンの画面を覗きにくる子…。驚くほどの好奇心と行動力、そして瞬時に遊びを作り出す想像力には感心した。身の回りの小さなことに興味を持つ楽しさは、彼らのほうが十分に知っている。後輩たちのそんな光景がとても頼もしく思えた。
先月、小6と中3を対象に行われた全国学力テストの結果が発表された。結果は良好との報告だ。ただその一方で、教育現場がテスト対策に振り回されていないだろうか。先生方が責任と自信、余裕をもって接することができる環境も守らなくてはいけない。
BayPRESS 809号 /2016年10月08日発行
重大な決定を他人任せに 病院移転は自らの考えで
「なれ合いや根回しで事を丸く収めるのではなく、都民の前で決定過程をつまびらかにする」。小池百合子東京都知事は所信表明でこう語った。そして「知事にも都議にも職員にも公僕の精神が求められる。公の意識を持たない者が個のために公益をねじ曲げてはならない」と強調した。
さて、桜ヶ丘病院の移転問題。清水庁舎と桜が丘公園とどちらが最適か。残念ながら田辺市長は、明らかにすべき過程を踏まなかった。清水区の将来を決める重大な決定過程を、他人任せにするという決定をした。
運営母体の理事長に対し、市長名でどのような公文書を手渡したのか。一連の経過を含め、当局から議会へ正式な説明はない。一体、どこで、だれと、このような筋書きを描いているのだろう。
もし、移転先を清水庁舎に決めれば、必然的に庁舎は解体。清水駅東口公園への移転計画が一気に現実味を帯びる。
田辺市長の思惑通りかもしれないが、それで良いのか?なぜ、自らの考えを自らの言葉で話せないのか。決定過程の説明責任を果たさない限り、公益をねじ曲げていると言われても仕方がない。