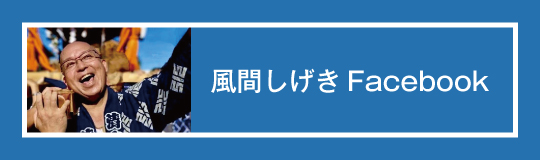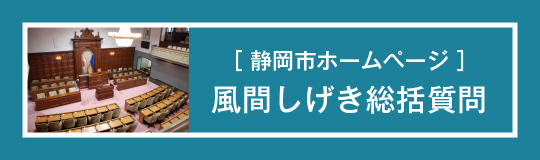プリズム
このまちの未来について、風間しげきが思うことを綴っていきます。皆様のお声もぜひ、お聞かせください。

BayPRESS 982号 /2026年01月31日発行
政党の政策と候補者の資質と 日本の進路決める重要な選挙
衆議院議員選挙の投開票は2月8日。日本の将来を左右する重要な選択となる
長引く物価高が家計を直撃し、「貧しい先進国」からの脱却は喫緊の課題だ。実質賃金の伸び悩みや国際競争力の低下に加え、人口減少と少子高齢化が進み、地方の担い手不足は深刻さを増している
厳しい財政制約の中で、社会保障の維持と成長投資をいかに両立させるか。もはや従来型のばらまきや業界依存の政治では、構造的課題には対応できない。既存の制度を抜本的に見直す、政治の「覚悟」が問われている。
さらに目を向けるべきは国際情勢。地政学的緊張の高まり、そして資源・食料を巡る国家間競争。安全保障の前提が揺らぐ中で、国益を守り抜く強固な意志も必要とされる。
しかし、聞こえるのは目先の人気取りや特定地域への利益誘導を優先する声だ
国家の行く末を決める代表を選ぶ選挙。各政党が掲げる公約だけでなく、候補者一人ひとりの「資質」も重要だ。
国民の痛みを理解し、国家の利益を自らの言葉で語り、実行できる政治家を選択する。その一票の積み重ねが、新しい日本を創る最も確実な一歩だと思う。
BayPRESS 981号 /2025年12月20日発行
巳から午へ変化と加速の年に 清水の未来へ共に駆ける一年
干支は巳年から午年へ。
平成26年の午年には、STAP細胞問題が社会を揺るがし研究への信頼性が問われたほか、ソチ五輪で羽生選手が金メダルを獲得するなど、話題が相次いだ年。また、日本創成会議が「消滅可能性都市」を公表し、人口減少が現実の課題として突きつけられた年でした。
さて、令和8年は「変化に対する対応が具体的に求められる年」に。国家として安全保障の位置づけが一段と明確になり、人口減少と少子高齢化が進む地方自治体では、対応と立て直しが強く求められる年になりそうです。
静岡市では大型建設事業が相次いで計画され、清水区では海洋・地球ミュージアム、清水庁舎の移転新築、新サッカースタジアムの建設計画などが進んでいます。その先に見える姿はどの様な風景か、そして負担は…。
新しい年の幕開け。「勢いよく駆け抜ける」「転換点をつかむ」といわれる午年。市政の情報も、より詳しく分かりやすくお伝えします。
スタッフ一同、皆様の努力が実を結び、笑顔で駆け抜ける一年となりますよう、心よりお祈り申し上げます。
BayPRESS 980号 /2025年11月22日発行
移転か改修か今年度末に結論 清水庁舎移転に約170億円
清水庁舎移転の説明会が12日、同庁舎の3階ふれあいホールで開かれ約100名の市民が集まった。
経過説明の後、難波喬司市長との質疑応答では、「わざわざ津波浸水想定区域に移転する必要はない」など、津波に対する不安の声が数多く聞かれた。
難波市長は、「大地震(南海トラフ型)にも耐える施設をつくるための移転」であること。そして津波に対しては「巴川の水門を10年を目途に建設、移転場所一帯の浸水被害を軽減する」ことなどを説明。
さらに、移転先となる清水駅東口に加え、エネオス側の開発も一体的に進めるとして理解を求めた。
移転新築案の場合費用は169億5千万円。現地改修案の場合は144億3千万円。
今後、現庁舎の耐震性能に対する評価や、移転に伴う駐車場整備、さらには移転した場合の現庁舎の扱いなど、細かな説明が不可欠だ。
難波市長は11月13日から始まった市議会11月定例会での議論や、パブリックコメント(12月5日必着QR参照)の内容を踏まえ、今年度末までに最終決定を下すとしている。

BayPRESS 979号 /2025年10月25日発行
誰もが安心して豊かに快適に 支えあいで福祉のまち清水を
「福祉のまつり2025」は「子どももお年寄りも、 障がいのある人もない人も、全ての市民が安心して豊かに暮らすことができる福祉のまちづくりには、 一人ひとりの自主的な福祉活動への参加が重要…」との趣旨で開催される。
ひらがなで表記することが多くなった、「障がい」の「がい」。
本市では平成24年度の障がい者計画などの策定時よりひらがなを適用。「一般的にマイナスイメージのある漢字をひらがなにすることで、障がいに対する理解を深め、共生社会を目指すことを目的とした」という。
また、かつてよく使われた障がいを「持つ」という表現も、最近では障がいが「ある」との表現に変わりつつある。
「持つ」は内面、「ある」は外部の状態をイメージさせる。
表現の変化は、偏見や差別、社会制度や日常生活の中の障害物こそが問題で、それらを取り除けば「誰もが安心して暮らしていくことができる」との考えからだ。
「子どももお年寄りも、 障がいのある人もない人も、全ての市民」が同じ立場で支えたり支えられたり。多くの市民が集い、福祉について考える年に一度の催し。えひご参加を。
BayPRESS 978号 /2025年09月27日発行
新スタジアム建設視野に合意書 試される地元経済界の本気度②
8月30日付の本コラムの記事中、エディオンピースウィング広島について「建設費約141億円のうち、法人募金が約100億円で70%、助成金が約35億円25% 個人募金が約6億円で5%」と書きましたが、これは「パナソニックスタジアム吹田」のデータで誤り。正しくは「建設費約286億円のうち、エディオンやマツダなど企業や個人からの寄付金が約
77億円で事業費の約27%」に訂止します。
報道等によると、寄付金約77億円のうち大半をエディオン30億円)とマツダ(20億円)が負担。国庫支出金が約80億円、県と市の負担が約100億円で財源の約6割強。使用料手数料が約27億円。
本市が想定する新スタジアム建設費は約300億円。仮に現スタジアム改修費124億円をあてたとしても、残りは176億円。県は「費用負担はしない」としており、広島同様の国庫支出金と施設使用料を見積もっても約69億円の不足。
さらに、興行収益をあげるための施設面での工夫や、賑わいの起爆剤となる商業施設などとの併設、複合化も不可欠。実現には寄付を含め、地元経済界を中心とした知恵と投資が必要と言えそうです。
BayPRESS 977号 /2025年08月30日発行
新スタジアム建設視野に合意書 試される 地元経済界の本気度
静岡市とエネオスは、清水製油所跡地の活用について合意書を締結。経済の活性化を基本に、相互協力で推進していく。
エネオス主体で土地開発を進め、市はスタジアムなど中核施設の用地の取得を検討。現スタジアムの大規模改修か、新スタジアム建設かの結論を、本年度末までにまとめる方針。
昨年3月に公表された市の試算では、現スタジアムの大規模改修が148億円、新スタジアムの建設に236億円とした。難波市長は「新スタジアムを含む投資のほうが、より大きな社会便益をもたらす」
とし「改修費の148億円が市負担の参考値」とも話した。
市は多機能なスタジアムシティを想定しており、事業規模は300億円以上と見込む。「実現には民
間投資が不可矢」と説明している。
市長が「一つの手本」とし挙げたのは、約2万8千人収容のエディオンピースウィング広島だ。
建設費約286億円のうち、エディオンやマツダなど企業や個人からの寄付金が約77億円で、事業費の約3割を占めた。
5月、静岡商工会議所を含む経済3団体が、市長に早期整備を要望した。今、地元経済界の本気度が試されている。
BayPRESS 976号 /2025年07月26日発行
減らす返すより成長戦略 真の政治力の結集に期待
7月18日、参院選も終盤。各政党は競って「減税」と「給付」を訴える。物価高騰への対応で、短期的に国民の生活を助けることは理解できるが、一時的な対症療法でしかない。
税金は教育や医療・福祉の充実、経済発展の好循環を作る原資。憲法で国民に納税の義務が課せられる理由だ。
経済は迷走し格差は拡大、高まる外交、安全保障面への不安。国連が公表した世界幸福度ランキング、日本は55位に後退している。
「減税」と「給付」は、言い換えれば大切な原資を「減らす」「返す」ことに他ならない。本来ならば、この状況から脱却するための、具体的かつ系統的な成長戦略こそ重要だ。
特に参議院は衆議院を抑制・補完、国会の審議を慎重にし、大所高所から中長期的視野で国政を論じる役割を担う。しかし実際は、衆議院のカーボンコピーで存在意義に欠ける。
党派の枠を超え、国の将来を考える政治家はどこに…。少なくとも、参議院はこのような人たちの集団であってほしい。
機能不全を起こしたこの国の政治。参院選を機に日本を根本的に立て直す、真の政治力の結集に期待したい。