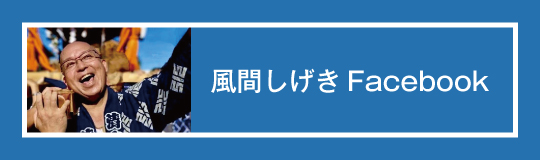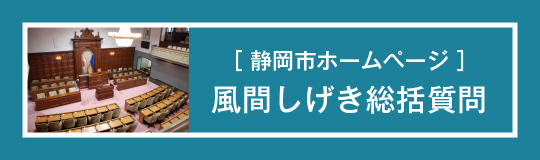プリズム
このまちの未来について、風間しげきが思うことを綴っていきます。皆様のお声もぜひ、お聞かせください。

BayPRESS 859号 /2018年12月22日発行
ワクワクする清水を BayPRESSは一心同体
2019年亥年。清水区においては大きく事が動く年となります。人口23万人。国際貿易港であると同時に、国際旅客形成拠点港を持つ清水は今、世界クラスの「場」の力を持っています。
今こそ、区民総がかりで清水の未来を考え、投資家さえワクワクする構想を、区民の手で作り上げたいですね。
「BayPRESS」は創刊39年を迎えます。より読みやすい紙面を目指し紙面体裁を大胆に刷新。また、読者参加の清水区限定のポータルサイトも公開間近。
スポンサーにとってもより身近な企業に成長するため、広告掲載費の見直しや、ポスティング業務の充実などにも積極的にとり組んでいきます。
BayPRESSは清水区の将来と一心同体。改めて経営理念を胸に刻み、力強く前に進んでいきます。引き続きご愛読ご支援をお願いいたします
♦︎経営理念♦︎
1.私たちは人と人とをつなぐ企業として「地域に密着」し、清水と共に発展していきます。
2.私たちは「信頼」される企業を目指し、いかなる時にも「誠実」に行動していきます。
3.私たちは全ての出会いに「学ばせていただく」という謙虚な姿勢でのぞみ、日々、人間力を高めていきます。
BayPRESS 858号 /2018年12月08日発行
新サッカー場建設視野に 清水駅東口には賑わいの施設を
29日、第5回清水庁舎建設検討委員会が開かれた。事業費は概算で85憶円から90億円。延床面積は約1万3千㎡。想定される職員数は650名。
委員からは「将来、無駄なモノを作ったと言われないよう、事業費や規模についてさらに精査してほしい」と言う意見が聞かれた。
その一方、商店街の衰退を心配し「何もしないよりも実行を」との意見もあった。
新庁舎建設で人の流れが変わるであろう事は否定しない。しかし、建設が周辺地域の賑わいに結びつかないことは、学識経験者を含め、委員の意見が一致するところだ。
庁舎建設予定地のJR清水駅東口公園は清水区の中でも発展が期待される一等地だ。この場所に、日の出地区に計画されている海洋文化拠点施設を建設してはどうか。約1万㎡と言われる民間用地を新たに購入する必要もなくなる。
さらに、同エリア一帯は、駿河湾フェリーの発着場を移転する計画や、東燃(現JXTG)の敷地に新サッカースタジアムを建設しようという構想もある。
陸と海、交通の結節点に大規模集客施設を立地すれば、土日閉庁の役所より清水区の活性化や賑わいづくりに確実に結びつくと思う。
BayPRESS 857号 /2018年11月24日発行
将来への備えは十分か 子どもたちのトチの実(下)
市案では、清水庁舎の建設予定地はJR清水駅東口公園。8階建てで延べ床面積1万3371㎡。事業費は約74億円。完成は22年末。
水族館と博物館を融合した「海洋地球に関する総合ミュージアム」は、東洋製缶跡地周辺約1万㎡を取得。開館は21年以降。年間来場者数を約60万人と想定。駐車場については周辺民間敷地で開発を誘導する。総事業費は数十億から百数十億円とも。
旧青葉小学校跡地で計画が進む歴史文化施設は、3階建と吹抜棟で延床面積は約5千㎡。総事業費は最大で60億円。開館予定は21年。
静岡市民文化会館の再整備の事業費は最大のケースで約174億円。2千席の大ホールや7千席のアリーナなどを整備。26年度完成を目指す。
市の公共建築物は12年4月末で4285棟230万㎡。築30年以上が55%、維持更新費は年平均で117億円。急速に老朽化が進み、今後30年間の維持更新費は総額で約9260億円との試算もある。
07年に330億円だった扶助費(生活保護や児童福祉等)は17年に646億円に。財政状況は今後厳しくなる。新しい施設整備に関しては、将来の負担と効果について明確な説明と市民合意が求められる。
BayPRESS 856号 /2018年11月10日発行
将来への備えは十分か 子どもたちのトチの実(中)
先日、東京の早稲田講堂で開かれた「全国地方議会サミット」に参加した。目的は野田聖子総務大臣の「地方創世の展望」と題した特別講演を聴くことだった。残念ながら大臣は国会日程により急遽欠席となったが、安田充総務省事務次官が議員に意識の転換を促した。
「2040年、人口減少に加え高齢者人口がピークを迎え、人口減少による労働力不足と高齢化で行政の運営が最も厳しい局面を迎える」。そして、「東京を含む地方自治体が崩壊する可能性がある」。
たとえば社会保障給付費、現在およそ121兆円なのが、2040年には190兆円、今の1.6倍に膨れ上がる。
安田次官は「地方自治体は、今の半数の公務員で行政を支える必要があり、自治体がそれぞれ個別にフルセットの機能を持つのではなく、いくつかの市町村が圏域を作り、施設などの役割分担を進める必要がある」と指摘した。
静岡市における人口のピークは1990年の73万9千人。2040年における人口推計は25%減の55万9千人。その上65歳以上が37%を占める。
果たして将来の備えは十分か。 次号は田辺市政が計画を進める大規模建設事業の規模と進捗状況を見ていく。
BayPRESS 855号 /2018年10月27日発行
将来への備えは十分か 子どもたちのトチの実(上)
宋に狙公という猿好きがいた。家計が厳しくなり餌のトチの実(どんぐり)を一つ減らそうと考えた。翌朝、「これからは朝に三つ、暮れに四つやる」と言ったら、猿が「少ない」と怒ったため「朝に四つ、暮れに三つにする」と言い直したところ、猿はとても喜んだ。
中国の故事「荘子」の一節だ。「目先の違いに気を取られ、結局は同じことであることに気づかない」ことのたとえ。
人口減少は国難ともいわれる。税収は減り、高齢者福祉や公共建設物の維持修繕費の増加など財政状況は今後一層厳しくなる。将来に対する有効な対策と備えが必要なのは、国も地方も同じだ。
安倍首相が消費税率を来年10月1日に現行の8%から10%に引き上げる方針を表明した。
静岡市では田辺市長が清水庁舎、海洋拠点施設、歴史文化施設、静岡市民文化会館の建て替え等、大規模な建設投資を行う方針を表明している。
いずれも「将来に備える」ための政策だという。この国、このまちを担う子どもたちのトチの実はそれで本当に増えるのか。
朝三暮四はまた、「口先で人をだます」という意味もある。子どもたちのトチの実を貪ることがあってはならない。
BayPRESS 854号 /2018年10月13日発行
地域特性に応じ備えを 大災害が複合的に発生
台風24号の影響で停電。外は漆黒の闇。荒れ狂う風が唸りながら家を叩いてくる。心から「怖い」と思った。台風一過。未だに断水や停電で不便な生活を強いられている市民も多い(3日現在)。記憶が褪せなうちに、すべての家庭で今一度、自然災害について考え直す機会にしてはいかがだろうか。
1959年に発生した伊勢湾台風(死者行方不明者5,098人)に代表されるように、かつては災害といえば台風だった。それが1995年に発生した阪神淡路大震災(同6,437人)、2011年に発生した東日本大震災(同22,233人)、そして平成30年7月豪雨(同230名)等によって、地震による液状化や津波、豪雨による氾濫、地滑りへの対応も急がれるようになった。
「想定を超える大規模災害は今後も必ず起こる」と強調する専門家は多い。
南海トラフ地震の30年以内地震発生確率は70%から80%に高まった。地球温暖化の影響で豪雨や台風などの災害も拡大していくという。
特に最近、多くの人が命を落とす大規模災害が複合的に連続して発生している。住んでいる地域特性を把握し、できる限りの備えをしておくことが大切だと思う...
BayPRESS 853号 /2018年09月22日発行
教員増やして 特別支援学級の悩み
市立小学校の特別支援学級を視察した。自閉症・情緒学級に通う児童数は8名。主要4教科のうち、社会と理科は通常学級に通うが、国語と算数は1年から5年の児童8名が一つの学級で授業を受けていた。
同校の校長は「子どもたちには個性、能力の違いもあり、学級担任と支援員各1名では、潜在能力を発揮させる十分な指導ができない」と顔を曇らせる。
教員や支援員の負担も重く「児童数が4名を超えたら、もう一名教員を増やしてほしい」との現場の願いは切実だ。
市教委では、文科省が特別支援学級の児童8名に教員1名と定めてることを理由にあげ、同省へ基準緩和の要望を続けていくとしているが早急な対応は難しい。
しかし、給与の国庫負担分等を含め、市が全額負担することを決めれば教師の追加配置はすぐにでも可能なはずだ。
現在、市立130の小中学校中、72校に418の特別支援学級がある。通学している児童生徒数は966名。
この5年間で知的、自閉症・情緒障がいの子どもたちの数は、増加傾向。弱者に優しい市であって欲しい。