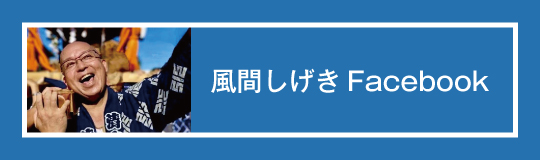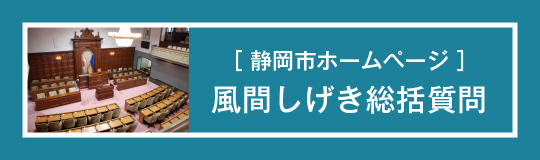プリズム
このまちの未来について、風間しげきが思うことを綴っていきます。皆様のお声もぜひ、お聞かせください。

BayPRESS 928号 /2022年03月12日発行
財政硬直で迫られる選択と集中 海洋拠点施設かスタジアムか?
凍結されていた海洋拠点施設建設事業が動き始めました。
展示コンセプトは駿河湾。入場料は大人1500円、子供料金750円。入館者数は初年度67万人、15年間で700万人を見込んでいます。 新年度予算には入館料収入を除く15年間の運営費70億円(年間4億6千万円)と、建設費100億円の計170億円を計上。建設費はマリナートの約76億円を抜き合併後最大規模。
経済界の強い要望もあり、「公共投資を呼び水に民間投資を促す」と意気込む田辺市長。しかし、周辺開発に係る民間投資の計画は不透明。また、大規模改修等、長期的な収支予測の説明も不十分です。
本市の財政は今後、人口減少にともなう税収減と、福祉関連費用の増大により硬直化が懸念されます。加えて、歴史博物館(46億円)、静岡市民文化開館改修費(160億円)など、大型建設事業がほぼ同時にスタート。新規事業には選択と集中が強く求めらます。
清水区ではサッカースタジアム建設計画も始動。水族館との複合化を含め、どちらに財源を集中するのか。
現下の社会情勢も踏まえ、慎重な検討が必要です。
BayPRESS 926 927号 /2022年02月26日発行
ポンプ場と文化施設で法令違反 揺らぐ信頼 倫理規範はだれが
市民や企業に対し法令順守を求める市役所で、法令違反が相次いでいます。
総事業費約70億円。清水区の浸水対策として工事が進む高橋ポンプ場建設計画では、事前着工など2度にわたり法令違反が発覚。また62億円で建設が進む歴史文化施設でも同様の法令違反。いずれも追加工事の発生や、完成時期が遅れる可能性が出ています。
こんな時こそ、行政のトップとして倫理規範を説くべき市長ですが、来年の市長選挙で有権者になる高校生に、本人の似顔絵入りマスクを配布したことが全国ニュースに。さらに、職員には「会食は家族や日頃行動をともにする少人数に限る」としながら、本人は県外の知人等と飲酒を伴う会食で感染。意識の緩みが指摘されています。
開会した2月定例市議会冒頭、田辺市長は施政方針で「市民の命と暮らしを守るため、引き続き感染防止や経済回復に全力を尽くす」と意気込みました。
相次ぐ法令違反と規範意識の緩み。ネット上には多くの批判が寄せられ、市政への信頼が大きく揺らいでいます。
次回は、日の出地区に建設予定の水族館建設事業を取り上げます。
BayPRESS 925号 /2022年01月29日発行
清々しい新年にも落ち着かない心 コミュニティを支え市政チェック
2022年初春。皆様はどのようにお過ごしでしたか。
私は、元旦早朝の所属分団の出初め式でスタート。岡八幡神社に初詣の後、管内で無火災祈念放水。 3日は母校野球部の現役激励試合を参観。試合後、侍ジャパンの岩崎優投手が、サプライズ登場。持たせて頂いた金メダルは、重さ以上に重く感じました。
清々しい新年になりましたが、心はどこか落ち着きません。オミクロン株の拡大で自治会も活動を自粛。飲食店など商店・企業も休業や廃業するところが増え、歴史ある商店街組織も休止や解散を余儀なくされそうです。
地域コミュニティ崩壊の危機。防止策を徹底、地元から経済を回していくことが重要です。コロナ禍でも仕事やボランティア活動に懸命に取り組む人たちを、ベイプレスは全力で支えていきます。皆様の支援もお願いいたします。
一方、市行政では厳しい財政状況にありながら、大型建設事業計画が復活する兆しです。無駄遣いはないか厳しい目でチェックしていきましょう。
明るい話題を積極的に取り上げていきます。身近な情報をお寄せください。
がんばろう清水!
BayPRESS 923 924号 /2022年01月01日発行
疑問や矛盾を積み残したまま 桜ヶ丘病院の移転計画可決へ
「撤退されないように…」。
桜ヶ丘病院のJR清水駅東口公園への移転について、田辺市長と、この計画に賛成する議員達は口をそろえる。今議会には、市が所有するJR清水駅東口公園と病院側が所有する大内新田の土地交換議案が上程された。議会最終日の採決では、賛成多数で採決される可能性が高い。議会は正式に移転計画を認めることになる。
田辺市長は、移転先は病院が選んだと話すが、この一連の計画をリードしてきたのは明らかに田辺市長だ。病院側にとって、建築費の2割を津波対策に割かなければならない危険な場所への移転は本望ではないはずだ。
疑問や矛盾は積み残されたままだ。
市と議会は、病院側が望んでいた経営が安定する場所と災害時医療が両立する場所につい真剣に議論してきたのか。この議決で清水庁舎は移転先を失うが、移転理由とした「一刻の猶予もない」耐震性能の問題はどこに消えたのか。さらに、「津波発生時でも病院は機能する」という、田辺市長の危機管理能力に、災害対策を任せる事ができるだろうか。
市長も議員も説明責任が問われている。
BayPRESS 922号 /2021年11月27日発行
11月27日は更生保護記念日 保護司の活動にもご理解を
担当する少年との面接、初めて少年院に行った。「先生のほうが緊張していますね」。法務教官に笑われた事を思い出す。
院内の自販機で買ったジュースを一本だけ差し入れることができた。久しぶりの「甘さ」だったのだろう。少年は時間をかけ味わっていた。責任の重さに肩が重くなった。
11月27日は更生保護記念日。1952年のこの日、東京・日比谷で更生保護大会が開かれた。犯罪をした人や非行少年を社会の中で支え、再犯を防ぎ自立と更生を援助するのが更生保護。この活動は静岡市で約130年前、実業家の金原明善らが静岡県出獄人保護会社を設立したことが源流とされる。
保護司は保護司法に基づき、法務大臣から委嘱を受けた非常勤の国家公務員。 現在、全国で約4万7千人、清水区では91人の保護司が活動している。
検挙された人に占める再犯者の割合は近年上昇を続けている。安全で安心して暮らせる社会を造る上で更生保護活動はますます重要になる。
その一方、保護司の人材確保が課題となっている。更生保護に理解ある、新しい仲間が増えることを願っている
。
BayPRESS 920号 /2021年10月23日発行
桜ヶ丘病院 移転計画で説明会 田辺市長は経緯について説明を
桜ヶ丘病院の移転に伴う住民説明会が、清水テルサ1階で開催される。
日程は①10月27日㈬15時~②19時~③11月1日㈪15時~の3回。各時間帯とも先着230名で、参加希望日の前日までに予約が必要。感染症対策のため参加は一人一回。
病院側は今回の説明会を「移転の経緯ではなく、計画中の新病院の医療体制と災害対策について説明する会」と位置付ける。
病院の移転場所は清水駅東口公園。この場所は、新清水庁舎の移転用地で、条例上、今なお庁舎が建設されることになっている。
昨年、市民から庁舎移転計画に関する住民投票条例の設置請求が出された際、田辺市長は「移転計画は市民への情報提供や、幅広い意見聴取を行うなど長い時間をかけ検討した」との理由で反対した。突然の方針転換。整合性もとれていない。田辺市長は経緯等について、市民に説明する機会を設けるべきだと思う。
住民説明会への参加希望者は希望の日時、住所、氏名、参加人員を明記しFAXでお申し込みを。
fax353・5317 お問い合わせは桜ヶ丘病院総務課
☎353・5311
BayPRESS 918号 /2021年09月11日発行
桜ヶ丘病院移転で住民説明会 問われる経過説明と市の責任
桜ヶ丘病院の内野直樹院長が、津波対策を含む新病院建設の基本的な考えを田辺信宏市長に書面で伝えた。
「建築費の2割を災害対策に充てる。最大浸水想定高2・7ⅿを上回る5・9ⅿに建物を嵩上げする。陸上交通途絶時に支援物資の搬入を可能とするヘリコプターのホバリングスペース(空中停止)を設置する。災害時には20床を床入院病床以外に設ける」(抜粋)というもの。
田辺市長は当初から建物の嵩上げとヘリ離着陸場の設置を移転計画の前提条件としてきた。
結果的に離着陸場は断られ、ホバリングスペース案が浮上。どれだけ熱心に交渉してきたのか。残念ながら会議録にその形跡は見当たらない。
市が誘導してきた清水庁舎の跡地への移転計画は二転三転。振り回されてきた病院側が、市のメンツを守るための尻ぬぐいをした形だ。
8月26日付静岡新聞朝刊は「10月めどに住民説明会」と報じた。市民が聞きたいのは病院の対応だけではない。市に求められる役割と経過説明だ。病院側への丸投げは許されない。
田辺市長は市民との対話を頑なに拒んできた。責任ある対応を望みたい。