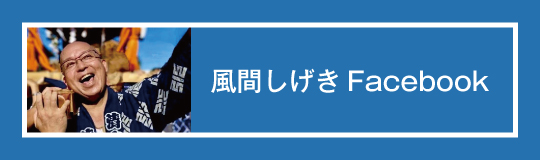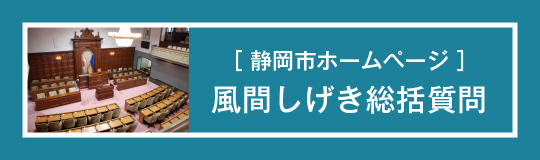プリズム
このまちの未来について、風間しげきが思うことを綴っていきます。皆様のお声もぜひ、お聞かせください。

BayPRESS 950号 /2023年05月27日発行
政策に根拠と裏付け重視 市政改革や見直しに着手
難波市長就任後、事業の打合せを行った職員は「田辺市政はパッション(情熱)重視、難波市政はエビデンス(根拠・裏付け)重視。政策の立案、進め方は180度違う」と話す。
政治判断には根拠や裏付けが不可欠なのは当然。「前市長を否定するわけではないが」と前置きしながら「これが普通なのかもしれない」と本音を漏らした。
改革や見直しが始まっている。「世界の大きな知を活かした行政執行研究会(仮称)」は6月からスタート。最新の科学技術に精通した有識者を集め、新事業の立案につなげる。
大規模施設事業の見直しも進む。海洋・地球総合ミュージアムは、これまでの博物館的展示ではなく研究開発への貢献など、公的施設として整備意義を重視した内容にする意向だ。
また、スタジアムについては、IAIスタジアムの改修費用を明らかにする一方、エネオス用地の課題や条件などを精緻に調べるため、直ちに調査実施事業者の公募手続きに入るという。
6月定例市議会初日の13日には所信表明が行われる。今後4年間の市政運営で静岡市がどこまで変わっていくのか注目していきたい。
BayPRESS 949号 /2023年04月22日発行
地域の力衰弱 危機的状況 市政と議会に意識改革必要
難波市長が大井川利水関係協議会に入会する意向を明らかにしたことに対し、自民党静岡市議団の鈴木和彦会長は、『もっと謙虚な人かと思っていたが、強引になってしまった。議会を尊重し、相談しながらやってほしいと注文を付けた』という。
『自民党市議団が今回の選挙で難波市長を全面支援した経緯がある』ことを踏まえ、4月14日静岡新聞が報じた。
難波氏は当選直後「特定の政党から支援を受けたからと言って、その意向に大きく影響を受けることは無い」と断言。 鈴木会長の発言は「議会」を「自民党市議団」に変えると筋が見えてくる。
人口減少率が、全国20の政令市中で最も高い理由につて、難波市長は「ハコモノや行政サービスの無償化は分かりやすいが、その一方で都市の基礎体力、体幹強化策は先送りにされてきた」と指摘。
「これまでの延長上の市政では地域社会の大きな力が衰弱してしまう危機的状況にある」とさえ話す。
「議会」は行政を監視する役割を十分に果たしてきのか。
難波市長の手腕に期待するとともに、旧態依然とした「議会」にも意識改革が求められている。
BayPRESS 947号 /2023年02月11日発行
関東大震災から百年 教訓新たに 本所防災館でパニック状態に!?
「忘れること」は健康法ともいわれています。嫌な体験や経験を忘れることで幸せな毎日が過ごせるとも言えます。でも、世代を超えても忘れていけない教訓があります。
先日、地区防災会の研修で、墨田区にある東京消防庁本所防災館に行ってきました。ⅤR防災コーナーでは特殊なゴーグルをつけて、地震、風水害を疑似体験したり、煙が充満する廊下を出口に向かって迷いながら逃げたり、手すりの無い部屋で四つん這いになり阪神淡路大震災の揺れを転がらないように耐えたり…。
これまで、様々な施設で似たような経験してきても、環境が変わると手順を忘れチョットしたパニック状態に。定期的に訓練、しっかりと記憶しておかないと、いざ、と言う時役に立たないことを実感してきました。
百年前の9月1日に発生した関東大震災での死者行方不明者は10万5千人。その後も、阪神淡路大震災では5千5百人、東日本大震災で1万8千人もの命が失われました。
南海トラフ地震での死者数は23万にと言われています。自然災害の教訓だけは風化させず、しっかりと伝え、備えておきたいですね。
BayPRESS 945号 /2023年01月01日発行
笑顔の絶えない一年に 「癸卯」は心機一転の年
ゆく年、くる年。
今年はどんな年でしたか。来年はどんな年にしたいですか。
振り返れば、新型コロナウィルスの感染拡大は日常生活に大きな影響を与え、台風15号は清水区に大きな被害をもたらしました。
23年の干支は「癸(みずのと)卯(う)」。 干支は古代中国で発達した陰陽五行説という、未来を予測するための統計学。
「癸」は植物の内部にできた種子が大きさを測れるまで大きくなった状態。「卯」
は茂。
繁栄をもたらす命が生まれ、繁栄していく年。縮んだバネが解き放たれ、一気に伸びていく、そんな年にしたいですね。
ベイプレスでは、エスパルスのJ1復帰に向けての戦いをはじめ、健康や福祉など清水の身近な情報を伝えていきます。
また、駅前銀座や清水銀座をはじめとする清水区の商店と区民の生活が密接に結びつくよう、双方にとってより良い賑わい作りにも、これまで以上により深く関わってわっていきたいと思います。
清水区の区民の皆様や、弊紙を支えていただく企業、商店の皆様が、笑顔の絶えない一年になりますよう。スタッフ一同、心よりお祈りい
たします
BayPRESS 943号 /2022年11月26日発行
清水庁舎は一転し 現地改修で 迷走の原因は強引な市政運営
清水庁舎の整備検討委員会は、現地改修をすべきとの決定をしました。そもそも、築40年に満たない庁舎を百億円近い税金を投じて新築する必要があったのでしょうか。
平成30年に策定された「新清水庁舎建設基本構想」。市当局は、清水庁舎は耐震性能が劣り、改修と新築の初期投資に維持管理費等を含めたライフサイクル(生涯)コストでは改修より新築が勝ると試算しました。
しかし、建築構造の専門家や市議会からは、清水庁舎は現庁舎の耐震診断が構造に適していないこと、また、耐用年数の検討も不十分で結果的に改修費が過大に見積もられている等の指摘がされてきました。
整備検討委員会の結果を受け、市の方針が改修に変更され今後、適切な耐震診断や積算が行われた場合、改修費は前回の試算より大幅なコストダウンが可能となりそうです。
なぜ、最初から十分な検討をしなかったのか。田辺市長の「結論ありき」の強引な市政運営が迷走の原因と言えそうです。
来春は静岡市長選挙。教育や福祉、災害対策の充実、そして確実に市の発展に結びつく政策論争を期待したいですね。
BayPRESS 940号 /2022年10月22日発行
市長自らの初動や判断を検証 豪雨災害を教訓に体制強化へ
今回の豪雨災害で被災し、今なお不自由な生活を強いられている方々に心からお見舞いを申し上げます。
田辺市長は一連のの災害対応に関し「判断は適切だった」と振り返り、職員は「想定を上回る雨量のため対応は不可能だった」と話します。
はたして、市長は事態を正しく理解し、あらゆる事態を想定、与えられた権限を迅速かつ適切に使うことができたのか。また、市の施設上の対策は十分だったのか。
平成30年年7月に発生した西日本豪雨で、甚大な被害に見舞われた岡山県では発災直後に検証組織を設置。関係職員への聞き取りをもとに「豪雨災害を教訓とした災害初期対応等の見直し」をまとめ対策を強化しました。
危機管理は想像力。市長や職員が批判されることを恐れ、自己弁護に終始したとき、市民は再び危険にさらされます。
災害の記憶が消える前に、市長自らの初動や判断を含め全て洗い出し、第三者の目で検証。その上で対策強化をすることで初めて「災害に強い静岡市」の実現が可能となるはずです。
市民の命を預かる意識があるのか。田辺市長の心構えが改めて問われています。
BayPRESS 937号 /2022年08月27日発行
活性化の核 稼ぐ施設として 清水に新しいスタジアムを③
現スタジアムの課題について、市の調査では、サッカー以外の収益源は限られる、アクセスが悪いなどの点が指摘されました。
収益性をあげるため他都市ではスポーツジムや保育園、ホテルやアリーナとの併設が進んでいます。
アクセスの課題は田辺市長のいう「JR清水駅東口のエネオスの所有地」が建設地となればクリアされるます。
エスパルスの新しいホームグラウンドとしてだけでなく、活性化の核、稼ぐ施設としてスタジアムを位置付けること。
霊峰富士と駿河湾を背にしたスタジアムは世界一のロケーション。この地で行われる試合やライブには、世界中から多くの人たちが集まり、宿泊施設はどこも満室、周辺の商店街や飲食店は賑わい、日の出や三保だけでなく、県内の観光地や施設にも多くの人たちが訪れるでしょう。
市はエネオスとの用地交渉を急ぐこと。水族館やアリーナなど計画中の施設をスタジアムに集約すること。
建設費用については商工会議所を中心とした経済界やサポーター、市民有志の具体的な動きを期待したいですね。