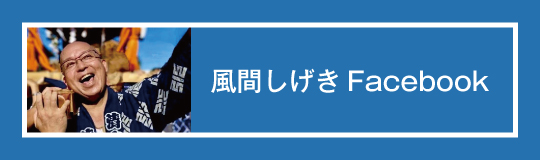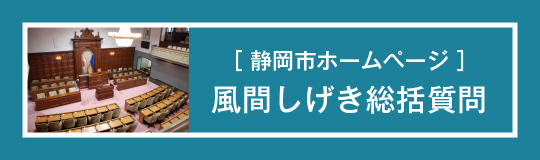プリズム
このまちの未来について、風間しげきが思うことを綴っていきます。皆様のお声もぜひ、お聞かせください。

BayPRESS 835号 /2017年11月25日発行
議会不信から不要論へ 改革に不断の努力を
「中学校の教科書にも書いてありますが地方議会は制度上、与党なんてないですよ」。姫路市で開かれた全国市議会議長会フォーラム。議会改革先進市、会津若松市議会の目黒章三郎議長は全国から集まった約二千人の市議を前にこう切り出した。自らを与党と称し市長の引き立て役になっている議員たちへの痛烈な皮肉だ。
「古いモノを見たければ博物館か議会へ行け」と言われないよう不断の努力を…。伊万里市議会の盛泰子前議長は「二度と定数削減を突き付けられない議会」を目標に改革に着手。緊張感の中で議員の資質が高まっているという。
いたるところで議会不要論さえ出ている。一方、「もし議会不信が表面化していないとしたら、『議会のドン』が自治体を牛耳っている証拠、むしろ最悪」。東大政治学研究科の金井利之教授はこう指摘した。
改革に前向きに取り組んでいる議会とそうでない議会、二極化は一層進む。「一般的に改革推進派は2割。中間が6割。反対派が2割。まずは積極的な2割で前に進め」と四日市市議会の豊田政典議長。
市民にとって本市の議会はどうだろうか。改革に向け不断の努力が必要だ。
BayPRESS 834号 /2017年11月11日発行
良心と覚悟、そして自信 澤田教一 戦場写真展
何が彼を動かしたのか…。IZU PHOTO MUSEUMで開催の「澤田教一 故郷と戦場」展に行った。
学生時代に澤田の残した一枚の写真に衝撃を受け、憧れた。UPI通信の報道カメラマン。1936年青森市生まれ、29歳で戦火の絶えないインドシナ半島に赴き、34歳の時、取材中にプノンペン近郊で銃殺された。
写真展のメインは1965年にベトナムの激戦地で撮影された「安全への逃避」。これこそ、私が衝撃を受けた一枚の写真だ。米軍の爆撃から逃れるため、幼い子供たちを抱え、必死の形相で川を渡る二組の親子。銃弾をかいくぐりながら撮影したこの写真が世界報道写真大賞、ピュリッツァー賞を受賞。彼を「世界のサワダ」に押し上げた。
さらに決定的な写真を撮るために、彼はより危険な戦場へ。その動機を、名誉欲や金銭欲、危険を乗り越えていく陶酔感と評する人もいた。
写真をじっくりと見ながら改めて考えた。彼を戦場に駆り立てたのは何か。それは、報道の「良心」と「覚悟」、プロカメラマンとしての「自信」であったに違いない。
文化の日、学生時代に戻ったような気分になった。
BayPRESS 832号 /2017年10月14日発行
誰に託すその一票 望ましい人間像は?
先日参加した勉強会で森信三氏が掲げた「望ましい人間像の」の五大条件を知った。
第一、自分一人で判断のでき る人
第二、人々と協調のできる人
第三、実践的な人
第四、常に国家社会と民族の運命について考える人
第五、さらに世界人類の将来について思念する人
森氏は京都帝国大学在学中、哲学者、西田幾多郎氏に学び、哲学者、教育者として戦後の教育界に影響を与えた。
衆議院議員選挙が公示された。意中の人はお決まりだろうか。きな臭さが増す世界情勢。国政に携わる候補者には、一、二、三は当然、常に国家社会と民族の運命について考え、さらに、世界人類の将来について思念、行動する人間を強く望みたい。
前回選挙(平成26年)の投票率は清水区で54.37%。実に半数近くが棄権した。果たして日本はそれだけ安全で、すべてに安心できる国なのか。
有権者が「選挙で政治は変わらない」という意識を変えない限り、子どもたちの将来は変わらない。
あなたは一票にどんな思いを託しますか。
BayPRESS 830 号 /2017年09月09日発行
地元にも有名な老舗メーカー 10月孫の日 ラン活もピーク?
「ラン活」という言葉、知っていました?「子供や孫にお気に入りのランドセルを贈りたい。」そんな思いのご両親、祖父母が早め早めにと予約、購入活動に入ることだそうです。
総務省の家計調査によると10年前、通学用カバンへの支出が最も多くなる時期が3月だったのに対し、数年前より夏頃から徐々に支出金額が増え、10月にピークを迎える傾向にあるとのこと。背景の一つが少子化。平均購入金額も年々上昇しているようです。
実は私も50と○年前、祖父母にランドセルを買ってもらいました。大切に使うべきランドセルに乗って滑り台を滑ったりと、相当罰当たりな使い方をしましたが、何とか6年間使うことができました。
こんな使い方は論外にしても、元気な子供たち、少々乱暴な使い方にも耐えうるものを選んであげたいですね。
10月15日の日曜日は孫の日(まごのひ)。通販を利用される方や、遠く県外のお店まで出向く方も多いようですが、アフターサービスが整っているかどうかは選択の重要なポイント。地元にも全国的に有名なランドセルの老舗メーカーがあります。ぜひ、足を運んでみてはいかがですか。
BayPRESS 829号 /2017年08月26日発行
最大限の備えで守った命 阿蘇医療センター視察
会派視察で阿蘇医療センターを訪ねた。前身は昭和25年設立の阿蘇中央病院。平成25年1月から本体工事が始まり、同26年8月開院。124床。鉄筋コンクリート造で外来棟は耐震、中央診療棟と病棟は免震構造。屋外には救急ヘリポートを有し総事業費は約49億円。
平成28年4月に熊本地震が発生した。この時、免震構造が威力を発揮した。建物を免振ゴムで地面から絶縁し振動を伝えない工法だ。他の耐震工法に比べ建設費用がかさむ。議会には反対の声もあったが、最大限の備えが患者の命を守った。
「免震構造を備え、また市内在住の常勤医師がすぐに駆けつけてきたことで、発災直後から救急車やヘリ搬送などで数多くの救急患者を受け入れることができた」と、胸を張る病院関係者。
また、救急ヘリポートについての質問には「屋上設置となると気象条件に大きく影響を受ける。患者の搬送も困難だろう」と話した。
田辺市長は桜ヶ丘病院の移転先を津波浸水想定地域にある市有地、清水庁舎とする方針を決めた。屋上ヘリポートや防潮堤等の周辺整備で災害に強い病院になると話す。具体的な説明を求めたい。
BayPRESS 827号 /2017年07月22日発行
お盆と「タギーへの手紙」 ちょっぴり悲しくなったら
盆の入りで迎え火を焚いて、送り火で霊を送る。故人の霊魂があの世を行き来する「精霊馬」(しょうりょううま)を供える。ご先祖様は今年も、迎え火を目印に、精霊馬に乗って来てくれたのかな。
「命って何? 死って何? どうして小さな子どもたちが死ななければいけないの?」。
エリザベス・キューブラー・ロスを知ったのは最近のこと。精神科医であり『死ぬ瞬間』の作者。ホスピス運動の発展に大きな役割を果たした。
『ダギーへの手紙』(佼成出版社)は、末期癌に侵された9歳の少年タギーが書いたロスへの手紙。この本は、少年への返事を元に書かれた。
「この世でやらなければいけない事を全部できたら、私たちは体を脱ぎ捨てることが許されるのです。その体はまるでサナギが蝶々を閉じ込めているように私たちの魂を閉じ込めているの」と語るロス。
「そして、ちょうどいい時期が来ると、私たちは体から出て自由になれるのです。もう痛いこともなく、怖がることもなく、悩むこともない」と…。
この時期になると、亡き肉親や友人との楽しかった思い出とともに、後悔や自責の念もよみがえり、ちょっぴり悲しくなったりする。名著だと思う。訳は、アグネス・チャン。
BayPRESS 826号 /2017年07月08日発行
庁舎検討市民公募始まる 可否を含め冷静に判断を
新清水庁舎建設検討委員会、市民枠(2名程度)の公募が始まった。市内に通勤・通学で18歳以上。申込書は各区役所ほか市のホームページからもダウンロードできる。7月28日(金)必着。一次選考は申込書、小論文の審査。通過者は8月9日(水)に面接。
テーマは「あなたの考える明日の清水に期待する庁舎の在り方」で800字程度。
さて、庁舎の移転新築に関する市民の意向はいつ確認したのか。百歩譲っても、検討委員会ではまず、移転の可否をしっかりと検証すべきだ。テーマの意図を推し量ると、移転に慎重な市民が選ばれる可能性は少ない。
桜ヶ丘病院の移転を念頭に、田辺市長が焦る気持ちは分かる。が、検討委員会そのものが出来レースだとしたら、最終局面で混乱を招く。
移転を否定するものではない。ただ、厳しい財政状況下概算で約120億円といわれる事業(桜が丘高校二校分)の必然性が本当にあるのか。
清水のまちの骨格が決まる。夢膨らむ海洋文化拠点構想の積極的推進は大いに結構。しかし、庁舎と病院の移転はそれぞれ冷静な判断が必要だ。
公募については市企画局アセットマネジメント推進課へ。